明治31年 (692首)
この年の2月から3月にかけて、子規は所属する新聞「日本」
に、「歌よみに与ふる書」を10回にわたって発表し、「仰せの如く近来和歌は一向に振い不申(もうさず)候、正直に申し候へば万葉以来実朝以来一向に振い不申候。」。「貫之は下手な歌よみにて、古今集はくだらぬ集に有之(これあり)候。」などと、古今集とその亜流の旧派を痛烈に批判した。
これに対して旧派の歌人やその同調者からの反論も激しく、子規の拠点である「日本」社内でも、子規に反対する者が多く、孤立無援、四面楚歌の中で、多数の論敵と闘わねばならなかった。
こうしたなかで子規は友人の漱石宛に、次のような手紙を書いている。「歌につきましては内外共に敵にて候、外の敵は面白く候へども内の敵には閉口致侯、内の敵とは新聞社の先輩其他交際ある先輩の小言に有之候、まさかそんな人に向かって理屈をのぶる訳にも行かず、さりとて今更出しかけた議論をひっこませる訳にも行かず、困却致候(以下略)」と、子規は珍しく弱音を吐いている。
だが、これしきのことに怯むような子規ではない。彼は「歌よみに与ふる書」と並行して、「百中十首」(自作の短歌百首の中から歌人、俳人、言論人ら11人の選者に1首づつ選んでもらう)を、11回にわたって「日本」紙上に発表して、短歌革新理論を実証してみせ、遂に反対派を沈黙させたのである。
今西幹一氏は著書「正岡子規の短歌の世界」の中で、「百中十首」其1〜其11の中から1首づつ選者別に次の11首を選んでいる。
其1 白雲 (五百木瓢亭) 選
椽(えん)先に玉巻く芭蕉玉解けて五尺の緑手水(てうず)鉢を掩ふ
其2 徒然坊 (坂井久良伎) 選
中垣の境の桃は散りにけり隣の娘きのふとつぎぬ
其3 某 (陸羯(くがかつ)南=新聞「日本」社長) 選
黒川の境にかける水車汲みてはこぼす山吹の花
其4 (河東) 碧梧桐 選
古庭の萩も芒(すすき)も芽をふきぬ病癒ゆべき時は来にけり
其5 (高浜) 虚子 選
榛(はん)の木に烏芽を噛む頃なれや雪山を出でて人畑をうつ
其6 (内藤) 鳴雪 選
豊葦原の瑞穂の国と天の神がのりたまひたる国は此国
其7 (梅沢) 墨水 選
官人の驢馬に鞭撻(むち)うつ影も無し金州城外柳青青
其8 戯道 (末永鉄巌) 選
病みて臥す窓の橘花咲きて散りて実になりて猶病みて臥す
其9 竹柏園 (佐佐木信綱) 選
寐静まる里のともし火皆消えて天の川白し竹藪の上に
其10 (石井) 露月選
望(もち)の夜は恋しき人の住むといふ月の面をながめつゝ泣く
其11 遠人 (福田把栗)選
行き暮れし真葛(まくず)が原の風寒み鶉(かっこう)鳴くなり人も通はず
其7
「官人の驢馬に鞭撻(むち)うつ...」は、子規が明治28年日清戦争に従軍したときの回想歌である。なお其3には同じく従軍時の回想歌「もののふの屍をさむる人も無し薫花咲く春の山陰」があるが、私は先の戦争でこれとよく似た光景を見ているので、感慨ひとしおである。
「百中十首」は子規の短歌革新の真価を世に問うものであっただけに、秀歌力作揃いであるが、なかでも其1の「椽(えん)先に玉巻く芭蕉...」は、芭蕉の葉が広がっていく様を鮮やかにとらえていて、写生歌の極致として「百中十首」中の代表作とされている。
子規が写生を短歌、俳句の基本に据えたのは、友人の画家中村不折から写生の重要性を聞き、それに共感して短歌、俳句についても写生によって、絵空事ではない事物の本質を活写しようとしたのだ。
この年には次のような子規ならではの歌がある。
世の人は四国猿ぞと笑ふなる四国の猿の子猿ぞわれは
足たたば不尽の高嶺のいたゞきをいかづちなして踏み鳴らましを
久方のアメリカ人の始めにしベースボールは見れど飽かぬかも
ベースボールを野球と訳したのは子規である。ただし、これを「ノボール」とよんだ。これは子規の幼名「升」(のぽる)をもじったものである。

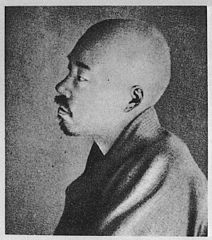 正岡子規は江戸末期以来の俗化した俳句の革新に努め、近代俳句を確立して、松尾芭蕉、与謝蕪村に並ぶ大俳人といわれていることは、広く知られているが、短歌においても風流韻事に堕した短歌を革新して、近代短歌の基礎を築いた超一流の大歌人であることは、一般にはあまり知られていない。
正岡子規は江戸末期以来の俗化した俳句の革新に努め、近代俳句を確立して、松尾芭蕉、与謝蕪村に並ぶ大俳人といわれていることは、広く知られているが、短歌においても風流韻事に堕した短歌を革新して、近代短歌の基礎を築いた超一流の大歌人であることは、一般にはあまり知られていない。